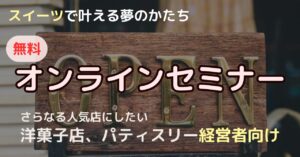「自宅で焼いたお菓子を販売してみたい」と思ったことはありませんか?
Instagramでスイーツ投稿をしていたら「売ってほしい」と言われたり、イベントで配ったクッキーが好評で「お店出したら?」なんて声をもらったことは?
でも、いざ始めようと調べてみると――
「営業許可がいる?」「自宅のキッチンじゃダメ?」「届け出ってどこに?」
そんな疑問や不安にぶつかり、足が止まってしまう方も少なくありません。
この記事では、副業でスイーツ販売を始めたい会社員や、これから開業を目指す個人事業主の方に向けて、自宅で焼き菓子を販売するために必要な法律・許可・届け出の方法をわかりやすく解説します。
読めば、あなたの「お菓子を仕事にしたい」という想いが一歩現実に近づくはずです。
目次
- 自宅で焼き菓子を販売するには許可が必要?
- 必須!食品衛生責任者と営業許可制度の基礎知識
- 自宅で営業許可を取るためのキッチン改修ポイント
- 「菓子製造業」か「飲食店営業」か?選ぶ許可の違いとは
- 開業後に気をつけたい保健所対応と集客の方法
自宅で焼き菓子を販売するには許可が必要?
「自宅で作ったクッキー、友達に売るくらいなら大丈夫だよね?」
そう思っていませんか?
私も最初はそうでした。Instagramにアップした手作りマフィンが思った以上に反響を呼び、「販売してほしい」とDMが届くようになったのがきっかけです。
趣味で作っていたお菓子が、誰かに喜んでもらえるなんて、こんなに嬉しいことはありません。
でも、販売しようと調べ始めた途端、分からない言葉ばかりが出てきて混乱したんです。
「食品営業許可」「保健所」「食品衛生責任者」「製造業登録」——
どこまで必要なの?どこに相談すればいいの?ネットの情報もバラバラで、なかなか前に進めませんでした。
結論から言うと、自宅で焼き菓子を「販売」するには、基本的に営業許可が必要です。
どんな販売形態であれ、「不特定多数の人に有償で提供する」場合には、法律で定められたルールに従う必要があります。
そのため、開業前には必ず保健所への確認と申請が必要です。以下でその内容を具体的に見ていきましょう。
【販売=食品衛生法の対象】
家庭用としてお菓子を作るだけなら許可はいりません。
しかし、**「お金をもらって人に販売する」時点で、「営業行為」**と見なされ、食品衛生法が適用されます。
【主な許可内容】
- 菓子製造業の営業許可
- 食品衛生責任者の資格取得
- 施設基準に合った厨房・製造スペースの設置
【許可が不要なケースもある?】
一部の自治体では、「シェアキッチン」や「加工業許可が不要な軽微な取引」など例外があります。
ただし、基本的には「営業許可ありき」で考えるのが安全です。
必須!食品衛生責任者と営業許可制度の基礎知識
「食品衛生責任者って資格が必要って聞いたけど、どうやって取るの?」
「そもそも“営業許可”って、どこで申請するの?」
初めてだと、言葉の意味すらわからないことが多いですよね。
焼き菓子販売を行うには、最低限この2つを押さえる必要があります:
- 食品衛生責任者の資格を取得すること
- 保健所で営業許可を申請・取得すること
【食品衛生責任者とは】
- 店舗や製造所に1人以上必ず配置しなければならない人
- 調理師・栄養士などの資格がない人は、1日講習(約6〜8時間)で取得可能
- 地方自治体の衛生協会で定期的に開催されており、費用は1万円前後
【営業許可申請】
- 管轄の保健所に相談・申請
- 現地調査・施設基準に基づくチェックあり
- 許可証が交付されるまでに1〜2ヶ月かかるケースも
【費用の目安】
- 許可申請費用:約16,000円〜20,000円(自治体により異なる)
- 食品衛生責任者講習:約10,000円前後
自宅で営業許可を取るためのキッチン改修ポイント
「自宅のキッチンを使っていいって本当?どこまで直せば許可が取れるの?」
SNSでは「自宅OK」と言ってる人もいれば、「専用キッチンが必要」とも言われます。何が本当なのか、迷ってしまいますよね。
営業許可が取れるかどうかは、キッチンの「構造設備基準」に適合しているかどうかにかかっています。
【保健所が見る主なポイント】
- 調理スペースが清潔・衛生的に保たれているか
- 家族と共用ではなく、事業専用スペースであること
- 冷蔵庫、洗浄設備、作業台などの配置と衛生状態
【よくあるチェック項目】
- 調理台・シンクが二槽式かどうか(地域により例外あり)
- 扉つきの収納・防虫防鼠対策
- 食品保管庫が個人用と分離されているか
- 換気扇・排水設備の整備
【キッチン改修にかかる費用例】
- 簡易的な改修:10万円前後
- 専用キッチンの設置:30万円〜
「菓子製造業」か「飲食店営業」か?選ぶ許可の違いとは
「焼き菓子の販売には“製造業”だけでいいの?」
「イベント出店やカフェもやりたいなら何が必要?」
目的に応じて、取得すべき許可が変わることを知らない人は意外と多いです。
焼き菓子を製造して販売するだけなら「菓子製造業」。
ただし、店頭で提供(カフェ営業等)もしたいなら「飲食店営業」も必要です。
| 営業形態 | 必要な許可 |
| 自宅で焼いて販売のみ | 菓子製造業 |
| 店舗内で食べられる形式(カフェなど) | 飲食店営業 + 菓子製造業 |
| イベント販売やマルシェ参加 | 地域により臨時営業許可が必要なことも |
【ダブル許可取得の注意点】
・申請書類が増える
・キッチンの構造基準がより厳しくなる
・複数の責任者配置が必要な場合も
開業後に気をつけたい保健所対応と集客の方法
「許可は取ったけど、これから何をすればいいの?」
「集客ってどうやるの?」
スタートは切れても、その後の維持や集客が一番のカギになります。
営業開始後も衛生管理を継続し、適切な集客導線を作ることが求められます。
保健所からの抜き打ち検査や更新手続きにも注意しましょう。
【営業後の注意点】
- 年1回の立ち入り調査がある地域も
- 変更(引越し・拡張・業態変更)時は再申請が必要
- 衛生管理記録や温度管理表の記録義務
【集客の基本】
- SNS運用(Instagram、LINE公式など)で魅せる写真・情報発信
- マルシェやネット販売サイト(BASE、STORESなど)との連携
- Googleマイビジネスに登録して、地元検索でヒットさせる
自宅で焼き菓子を販売するには、しっかりとした許可取得と衛生管理が必要不可欠です。
とはいえ、一つひとつのステップを丁寧に踏んでいけば、決して難しいことではありません。
あなたの作ったお菓子が、**「ただの趣味」から「誰かに喜ばれる仕事」**に変わる瞬間は、すぐそこにあります。
まずは管轄の保健所に問い合わせて、第一歩を踏み出しましょう。
◆ パティスリークラブでは、洋菓子店、パティスリーの経営者のための
無料オンラインセミナーを随時 開催しています。
・洋菓子店の開業を予定されている方
・お店の売上を上げたい方
・集客アイデアが欲しい方
・素材にこだわりたい方
・お客様に感謝されながらより良い店舗経営を楽しみたい方は
ぜひ下記のページからオンラインセミナーの詳細をご覧ください